| |
 |
| |
 |

土佐神社の名前は「延喜式」の中の「都佐坐(とさにいます)神社」という名前に由来している。 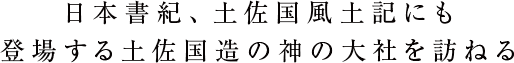

朱色の美しい鼓楼は、藩政時代初期の建築で、
力強いデザインが特徴。
全国にある古社、大社の多くは古代の豪族と深く関わっています。即ち、古社、大社の歴史は、豪族の歴史でもあると言うことができます。
土佐神社は雄略天皇の頃(460年頃)の創建で、土佐の総鎮守(一の宮)として、皇室の崇敬も厚かった神社であったと伝えられています。土佐神社に祀られているのは一言主神(高鴨神、賀茂氏一族)ですが、日本書紀(720年)には、その由来について興味深いエピソードが残されています。それは、葛城山の一言主神が天皇と共に狩りを楽しんでいた時に、獲物を巡って争いになり、ついに天皇の怒りをかって土佐に流されたというものです。この一言主神は、味鋤高彦根神(あじすきたかひこねのかみ/大国主神の子)ともいわれ、土佐(都佐)の国造の祖先とも伝えられています。また、「土佐風土記」には一言主神を祀る土佐高賀茂神社名が登場し、ここにも豪族らしき名前を見ることができます。
これらの物語の詳細はともかく、土佐の歴史は大和から移り住んだ一族によって始まったと想像することができます。
現在の土佐神社の社殿は、元亀元年(1570年)に長宗我部元親が再興、後に山内氏が修復、増設したもので、武門の信仰が厚かったことを物語っています。また、一言主神は「悪事も一言、善事も一言、言いはなつ神」といわれ、その性格は武士(もののふ)に通じるものがあり、土佐人の性格にも通じているようです。

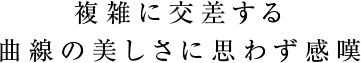
楼門をくぐり、長い参道を進むと、やがて大鳥居と社殿が見えてきます。荘厳な社殿は「入りトンボ」と呼ばれる様式で、入母屋造りの全面に向拝を設けた本殿、その全面に十字形の幣殿と拝殿を配して、トンボが本殿に向かって飛び込むような姿になっています。ただし、その大きな構造は空からでなければ確認は困難です。それでも、拝殿から脇に回り込むと、美しい大屋根のそりを見ることができ、複雑に交差する曲線の美しさに思わず感嘆します。

敷地内の厳島神社。神域の深い森には、
一言主神を慕う神々が集う。
そして、味鋤高彦根神は、大国主神の子ということで、国土開拓、農工商などあらゆる産業の繁栄の神様とされ、一言主神は、和合協調の神として一言で物事が解決されるということで信仰されている神様です。こうしたご利益があると伝えられることから、毎年8月24、25日の「しなね様」の大祭は参道も境内も埋め尽くすほどの人出で賑わいます。
商売繁盛を祈願すると言ってしまえばそれだけですが、土佐神社が発するエナジーは、そうした祈願にとどまるものではありません。いわば高知そのものの礎としての存在があります。 境内に足を踏み入れると、何かに包まれ守られているように感じるのは、決して錯覚ではないということです。
 |
高知県高知市一宮 |
| |
|
|
|
|







