| |
 |
| |
 |

若宮八幡宮の参道に立つ長宗我部元親像。元親22歳の初陣の姿。
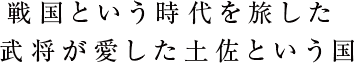
本誌の読者は、人気ゲームの「戦国 BASARA バトルヒーローズ」の長宗我部元親と言っても何のことだか分からないという人がほとんどかもしれません。しかし、このキャラクターの人気は高く、高知を訪れる若い世代に限れば、坂本龍馬と人気を二分すると言っても過言ではありません。司馬遼太郎のファンであれば「夏草の賦」の長宗我部元親と言えば思い出される人も多いはずです。世代的なギャップはさておき、長宗我部元親といえば、長身で強く美しい武将がイメージされるはずです。
高知県で長宗我部といえば、秦の始皇帝を祖とする秦河勝(聖徳太子のブレーンとされる人物)の血筋と伝えられ、元親は、その20代目。そして、長宗我部元親といえば、一領具足(半農半士)集団を率いて四国統一を果たした人物。徳川から領地として土佐を与えられた山内氏とは格が違うと考える土佐人は今も少なくありません。

若宮八幡宮。元親初陣の時の祈願をした神社。鎌倉時代の創建で、
土佐国吾川郡一帯を京都の六條若宮八幡宮神領地として奉納して祀られた神社。
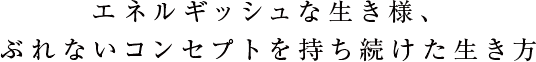

元親が 1588 年頃まで居城とした岡豊城址。
敷地内には現在、歴史民俗資料館がある。
天正3年(1575年)、まず土佐を統一した元親は「土佐の出来人」と評されましたが、織田信長と同盟を結び、四国内に兵を進める頃には鬼神よりも恐れられ、南予では明治の頃まで腕白な子供を諌める呪文として「ちょうそかべがくるぞ」と言われたそうです。そして、天正 8年(1580年)、元親の勢力拡大に危機感を覚えた信長勢に攻められますが、天正10年(1582年)に本能寺の変が起こり窮地を脱出。数々の危機に遭遇しながらも、天正13年(1585年)遂に四国統一を成し遂げます。元親は、慶長4年(1599年)病に倒れるまで、挫折と栄光を繰り返しながら生涯を過ごしますが、そのエネルギッシュな生き様、ぶれないコンセプトを持ち続けた生き方は、文頭のエピソードに繋がります。
長宗我部の家紋は、七酢漿草(ななつかたばみ)と呼ばれるもので、田園でよく見られる草(三つ葉)の文様です。一領具足と七酢漿草を並べてみれば、元親の戦の目的も農業振興であったと想像できます。また、ある戦で兵糧として敵地の麦畑を刈り取ろうとしていた家臣に、農民のために半分だけ刈るようにと指示したという話も残っています。368冊からなる天正地検帖も残しています。
つまり、農業こそ、国造りの基本と考えていたということは間違いありません。元親が、今日の高知に遺したもので最大のものを挙げるとすれば、それも、やはり農業に対する熱い思いではないでしょうか。もちろん、高知では漁業も、林業も盛んです。元親は海軍を所有し、その船で鯨を獲り豊臣秀吉に献上して大いに驚かせたという逸話も残っています。それでも、平野が少ないにも関わらず豊かな農業が営まれてきたのは、元親の熱い思いの継承のような気がします。つまり、土佐人のエナジーは田園をベースに受け継がれているということです。
右写真:浦戸城址は長宗我部氏の最後の居城の跡。
関ヶ原後、土佐に入った山内氏に長宗我部の
家臣が最後まで抗戦した地でもある。
敷地内には現在、坂本龍馬記念館がある。
| 長宗我部の土佐 Chosokabe no Tosa |
 |
高知県南国市岡豊町 |
| |
|
|
|
|







